
【2025年版】住宅ローン減税は省エネ基準がカギ!控除額・条件を徹底解説
このコラムでは住宅ローン減税の控除額や条件を細かくお伝えしていきます。
2025.06.16

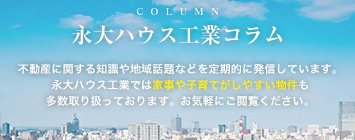

不動産売却に必要な費用は、仲介手数料・譲渡所得税・印紙税・抵当権抹消登記費用など多岐に渡り、相場は売却価格の4~6%程度です。
ただし、費用によって、支払いのタイミングや必要額の計算方法が違います。
必要なタイミングで適切に支払いができないと、売却手続きも中断してしまうため、不動産売却をする際は、どういった費用が必要なのか、いつ・いくら払えば良いのかを知っておきましょう。
本記事では、不動産売却に必要な費用の一覧やその相場、支払い額の計算方法、売却時にかかる費用や税金を抑えるポイントを解説していきます。
不動産売却の費用は、大きく分けると、売却時に払うものと、売却後の支払うものの2種類です。
不動産の売却時にかかる費用としては、不動産会社に支払う仲介手数料や物件のクリーニング費用、売買契約書に添付する収入印紙の購入費、抵当権抹消登記の費用などが存在します。
一方、不動産の売却後にかかる費用は、譲渡所得税・住民税といった売却利益に対する税金と、引っ越し費用がメインです。
不動産売却費用の種類と、金額の目安を見ていきましょう。
| 費用 | 金額の目安 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 売却価格×3%+6万円と消費税 |
| 譲渡所得税・住民税 | 不動産売却利益の39.63%または20.315% |
| 印紙税 | 1万円(売却価格1,000~5,000万円の場合) |
| 抵当権抹消登記費用 | 土地・建物一つあたり1,000円 |
| 司法書士報酬 | 1~2万円 |
| 住宅ローンの一括返済手数料 | 0~3万円 |
| 引っ越し費用 | 時期・人数・運搬距離等による |
| その他 | ケースバイケース |
上記費用を合計すると、おおよそ不動産売却価格の4~6%になります。
仲介手数料は、不動産会社に集客や契約書作りを頼み、無事に土地や建物を売却できたときに支払う手数料です。
一般的に、売買契約の締結時と、不動産の引き渡し日の2回に分けて支払いを行います。
宅地建物取引業法という法律で上限額が定められているため、「不動産の売却価格×3%+6万円と消費税」を超えるお金は請求されません。
仮に、不動産を3,000万円で売却した場合は、
・3,000万円×3%+6万円=96万円
・96万円×消費税10%=105.6万円
かかります。
譲渡所得税と住民税は、不動産売却の利益、譲渡所得に課される税金です。
以下の計算式で求めた譲渡所得に、税率をかけると納税額が分かります。
・譲渡所得=不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)
・納税額=譲渡所得×(譲渡所得税率+住民税率)
取得費は、不動産を買ったときに支払った経費で、不動産の本体価格や購入時の仲介手数料、登記費用などの合計です。
譲渡費用は、不動産売却時にかかる仲介手数料等の経費を指します。
譲渡所得税と住民税の税率は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の2種類です。
税率は「不動産の所有期間」で決まり、不動産を売った年の1月1日時点で、不動産の所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年超の場合は長期譲渡所得となります。
| 譲渡所得税率 | 住民税率 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 30% | 9% | 39% |
| 長期譲渡所得 | 15% | 5% | 20% |
また、譲渡所得税に復興特別所得税の2.1%が加算されるため、最終的な短期譲渡所得の税率は39.63%、長期譲渡所得の税率は20.315%です。
売買契約書に添付する、収入印紙の代金となっています。
売却価格に応じて金額が変わり、最小で0円、最大で60万円の納税が必要です。
ただし、印紙税額が10万円を超えるのは、不動産価格が1億円を超えるケースに限られます。
ほとんどの不動産は、1,000~5,000万円の範囲内で売買されており、この場合の印紙税は原則2万円なので、実際の負担はそれほど大きくありません。
また、2027年3月31日までの取引は、軽減税率が適用されます。
2万円の印紙税が1万円まで減額されるため、さらに負担は小さいです。
抵当権は、住宅ローンの滞納が続いた場合、金融機関が借金の担保として物件を差し押さえ、売却する権利のことを指します。
抵当権は登記というシステム上で管理されており、登記を変更する際は手数料が必要です。
このときの費用として、土地・建物ひとつあたり1,000円かかります。
抵当権が付いたままだと不動産を売却できないため、住宅ローン返済中の家を売るときは、必須の費用です。
抵当権抹消登記などの登記手続きを、司法書士や弁護士といったプロに頼む際、1~2万円程度の依頼料がかかります。
抵当権の抹消登記は、住宅ローンの完済後、つまり売却代金を受け取ってから行う手続きです。
売却代金でローンを完済する場合、物件の引き渡し日に決済と登記の両方をスムーズに終わらせる必要があり、売り主が自身で手続きするのは困難なので、司法書士報酬を払ってプロに作業を頼むことになります。
不動産売却代金で住宅ローンを一括完済する場合、金融機関から返済手数料を求められるケースが多いです。
金融機関によって、金額や手数料の有無は違いますが、一括返済手数料の目安は、おおよそ3万円。
繰り上げ返済手数料が無料の銀行でも、ローンの一括完済時は手数料がかかるという規約になっている金融機関は少なくありません。
売却と同時に住宅ローンを完済する場合は、事前に金融期間に問い合わせて、返済手数料や手数料の支払い方法を調べておきましょう。
不動産売却費用として、引っ越し料金も必要です。
引っ越し費用は、家族の人数や新居までの移動距離、繁忙期かどうかといった様々な要素で変わります。
単身者で短距離の引っ越しなら、3~5万円で十分ですが、4人家族である程度荷物があれば、10~15万円は必要です。
特に、引っ越し業者の繁忙期である2月から3月は、料金が通常期の倍以上になることも珍しくはなく、予約も中々取れません。
売却と引っ越しのタイミングがずれると、仮住まいが必要となり、さらにお金がかかるので、買い主が決まったら、早めに見積もりを取って引っ越し業者を抑えましょう。
不動産売却に関連するその他の費用としては、以下のようなものがあります。
・土地の測量費
・建物の解体工事費用
・リフォーム費用
・修繕費
・ホームインスペクションの費用
・ハウスクリーニングの費用
・粗大ごみの回収費用や家電のリサイクル費用
これらの費用は、人によって要不要が変わるお金です。
例えば、境界線があいまいで分かりづらい土地は、そのまま売るよりも、売り主負担で測量を行った方が、買い主を見つけやすくなりますし、売却価格も高くなります。
同様に、建物を解体して更地にしたほうが高く売れる物件もあれば、リフォームで大幅な売却額アップを見込める物件もあるため、物件に合わせて考える必要があるのです。
ただし、売却時にお金をかければ、高く売れるわけではありません。
物件によって、どこにお金を使えばより良い売却結果につながるかは違うため、不動産会社に相談して、コストパフォーマンスの良い支払いとそうでない支払いを見極めましょう。
不動産を売って利益が出ると、譲渡所得に応じた譲渡所得税と住民税の納税が必要です。
しかし、日本の税制には、「マイホームや相続した空き家を売ったとき、譲渡所得から3,000万円控除できる特例」があります。
この控除を使うと、譲渡所得3,000万円以下の取引なら、売却結果が黒字でも譲渡所得税と住民税がかかりません。
・不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除3,000万円
上記の計算を行い、譲渡所得が残る場合にのみ税金を納めます。
・マイホームまたは相続した空き家の売却であること
・不動産を売った年の前年・前々年に同じ控除を受けていないこと
・親子や夫婦などの親しい相手への売却ではないこと
など、いくつかの利用条件をクリアし、確定申告をすれば利用可能です。
不動産売却時に使える節税の特例の中で、トップクラスに使いやすく、節税効果も大きいため、積極的に利用しましょう。
通常、不動産売却時にかかる譲渡所得税と住民税の税率は、
・所有期間5年以下:39.63%(譲渡所得税30%+住民税9%と復興特別所得税2.1%)
・所有期間5年超:20.315%(譲渡所得税15%+住民税5%と復興特別所得税2.1%)
のどちらかです。
ただし、マイホームの売却で、物件の所有期間が10年を超えている場合、軽減税率の特例を適用し、税率をさらに下げられます。
・譲渡所得6,000万円以下の部分:14.21%(譲渡所得税10%+住民税4%と復興特別所得税2.1%)
・譲渡所得6,000万円超の部分:20.315%(譲渡所得15%+住民税5%と復興特別所得税2.1%)
また、10年超所有軽減税率の特例は、3,000万円の特別控除と一緒の適用可能です。
譲渡所得から3,000万円控除し、残った譲渡所得に対する税金を軽減税率で下げられるため、大幅な節税効果を見込めます。
現在住んでいる家を売却して、新居に買い替える場合、特定の居住用財産の買換え特例という制度を利用可能です。
特定の居住用財産の買換え特例は、本来なら不動産の売却時に納める税金を、新居の売却時まで繰り延べられるという制度。
一時的に納税を先送りにすることで、不動産売却代金の多くを新居の購入資金に回せるので、資金繰りが楽になります。
ただし、買い換えを不動産売却の翌年末までに終わらせること、売却する物件の所有期間が10年以上であることなど、売る家と買う家の両方に条件があるため、注意が必要です。
また、買い換え特例は、あくまでも納税を将来に繰り延べているだけなので、非課税にはなりません。
将来新居を売るときに、税金がかかります。
譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は、マイホームの売却で赤字になった場合、赤字分を控除として本業の給与所得や事業所得から差し引けるようにしてくれる制度です。
不動産売却で出た赤字の分だけ、給与所得や事業所得が減り、税金が安くなるため、制度を利用すると経済的な負担を抑えられます。
また、1年で赤字分を控除しきれない場合は、繰越控除といって、3年間に渡って控除を繰り越し可能です。
住宅ローン返済中の住まいを売却し、なおかつ売却額がローン残高を下回るとき限定の制度ですが、不動産売却の損失を埋め合わせられる特例なので、条件が合えば利用しましょう。
実力のある不動産会社と契約し、物件の高額売却を目指すのも、売却時の費用を抑える効果的な手段です。
不動産を高く売ると、その分仲介手数料等の費用も上がってしまいますが、手元に残る金額が増えるため、結果的に売却時の費用負担は小さくなります。
また、高額売却できる不動産会社なら、悪徳業者のように、不動産を買い叩かれて損したり、仲介手数料以外の報酬を請求されたりする心配もありません。
不動産会社の実力には幅があるため、相見積もりを取って、契約する会社を選びましょう。
実績が豊富で営業年数が長い、相場に合った査定ができる、売却プランを具体的に提案してくれるなど、複数の業者を見比べることで、良い業者を見つけやすくなります。
・不動産売却で利益が出て課税される場合
・節税の特例を利用する場合
・譲渡損失の損益通算や繰越控除をする場合
上記のどれかに当てはまるなら、確定申告が必要です。
そして、確定申告の手続きができるのは、不動産を売った翌年の2月半ばから3月15日までの1ヶ月間。
3,000万円の特別控除や損益通算といったお得な節税制度は、「確定申告すること」が利用条件となっていますし、期限内に申告できないと延滞税等もかかるため、不動産を売った後は、早めに申告の準備を始めましょう。
不動産売却には、仲介手数料や譲渡所得税といった様々な費用がかかります。
一般的な費用の目安は、おおよそ売却価格の4~6%です。
物件によっては別途お金がかかる場合もあるので、不動産売却で赤字にならないように、各費用の見積もりは早めに取りましょう。
また、信頼できる不動産会社の力を借りて家を高く売れば、費用負担を抑えられます。
確定申告をして節税の控除を利用すれば、譲渡所得税・住民税といった税の節税も可能です。
費用を抑えられるかどうかで、不動産売却後手元に残る金額が変わるので、不動産を売るときは、損しない取引を目指しましょう。
永大ハウス工業では、仙台・宮城エリアに特化した戸建て、マンション、土地など様々な不動産を取り扱っております。こだわりの物件はコチラから。

このコラムでは住宅ローン減税の控除額や条件を細かくお伝えしていきます。
2025.06.16

今回は、失敗しない物件選びのための「内見時に必ずチェックしたい10のポイント」を解説します。
2025.06.15

今回は、「頭金ゼロで家を買う」ことのメリットとリスク、その対策までを徹底解説いたします。
2025.06.12

ここでは、「価格動向」「住宅ローン金利の最新情報」「ライフプランから考えるタイミング」を中心に解説していきます。
2025.06.10