
【2025年版】住宅ローン減税は省エネ基準がカギ!控除額・条件を徹底解説
このコラムでは住宅ローン減税の控除額や条件を細かくお伝えしていきます。
2025.06.16

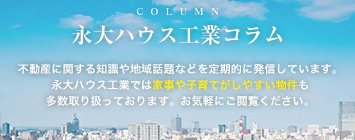

不動産を安く手に入れる方法の一つに、「競売物件を買う」という選択肢もあります。
ただ、競売物件は通常の不動産売買とは性質が異なるため、誰でも手を出して良い物件とはいえません。
リスクや注意点を把握したうえで、慎重に検討することが大切です。
ここでは競売物件のメリットや注意点、物件の探し方、「公売物件」との違いなどをまとめてお伝えします。
競売物件とは、住宅ローンの返済ができなくなった債務者の不動産を、金融機関の申し立てで裁判所が差し押さえ、強制的に売却される物件のことです。
競売は裁判所が主催し、基本的には誰でも参加できます。
物件は競りにかけられ、価格がもっとも高かった人に落札される仕組みです。
なお、売却代金は債務者である金融機関に配当され、住宅ローンなどの借金返済に充てられます。
競売物件は、相場より安く購入できることがメリットの一つです。
価格は競りで決まるため物件にもよりますが、市場の不動産より3~4割くらい安い価格で落札されるケースが多いです。
競売物件には、比較的きれいな状態の物件もあります。
こうした物件を落札できれば、リフォームやリノベーションの費用を抑えられ、快適な家をリーズナブルな価格で手に入れることも可能です。
また、売買手続きを簡略化できることもメリットといえます。
通常の不動産売買では、所有権の移転登記などの手続きが必要ですが、競売物件では裁判所が手続きを行うため落札者の手間を省けます。
司法書士などの専門家に依頼する必要もなく、諸費用を抑えられることもメリットです。
安い不動産物件には、それなりの理由があるものです。
競売物件も、以下のリスクや注意点がありますので、しっかり理解した上で購入を検討するようにしましょう。
不動産売買では、購入希望者が物件を内覧してから購入の可否を決めるのが通例です。
中古物件で居住者がいる場合でも、室内を見せてもらえます。
しかし、競売物件の場合、競売にかけられた時点では居住者が住んでいるケースが大半です。
しかも居住者の意思に反して強制的に売却される物件ですから、居住者が内覧に協力してくれません。
競売物件で購入前に確認できる情報は、裁判所が作成した「現況調査報告書」「評価書」「物件明細書」(いわゆる「3点セット」)だけです。
物件の種類や状況、周辺環境や評価額といった書面の情報をもとに、入札価格を決めることになります。
一般的な不動産物件の場合、住み始めてから一定期間内に住宅に欠陥が見つかった時は、売主が責任を負う「瑕疵担保責任(契約不適合責任)」があります。
新築はもとより、一部の中古物件でも瑕疵担保責任を追及できるのが通例です。
しかし、競売物件は、裁判所が差し押さえたものですから、売主(不動産の売却者)がいません。
また、今まで住んでいた居住者はお金がないため、欠陥があっても責任を追及できません。
そもそも内覧もできないわけですから、落札前に欠陥を探すことすら難しいのです。
競売物件の中には雨漏りがしたり、給排水設備が破損して水漏れがしたり、シロアリ被害に遭っていたりする物件もあります。
こうした修繕費用は、すべて落札者の自己負担です。瑕疵があっても、売買契約の取り消しや損害賠償請求はできません。
最も面倒なのが、居住者(債務者)に「引き渡しの義務がない」ことです。
競売は裁判所が強制的に行うものですから、債務者には売却の意思がありません。
また、裁判所は競売手続きや所有権移転登記などは行いますが、物件の引き渡しまで対応してくれません。
そのため、居住者が落札後も居座るケースが多々あるのです。
この場合、落札者は居住者に立ち退き交渉をする必要があります。
債務者には引き渡しの義務がないため、退去を拒否することも考えられます。
その時は債務者と話し合って退去してもらったり、裁判所に強制執行を申し立てたりと、落札者の手間と費用がかかることも注意が必要です。
競売物件と似たものに「公売物件」という不動産があります。
公売物件とは、税務署や国税庁、役所が法律に基づいて売却する不動産のことです。
競売物件は住宅ローンの滞納で差し押さえられた不動産ですが、公売物件は「税金や保険の滞納」で差し押さえられた物件をいいます。
公売物件も入札方式で、一番高く値をつけた人に落札されます。
価格は競りで決まりますが、市場価格より安くなることが多いようです。
ただ、競売物件と比べてきれいな物件が多いといわれ、物件によっては市場価格と同じくらいの不動産もあります。
公売物件のメリットや注意点は、競売物件とほぼ同じです。
内覧できないケースが多いですし、債務者への責任追及もできません。
引渡しの義務がないため、落札後も居座っている場合は立ち退き交渉が必要です。
なお、競売物件のように裁判所による強制退去はできません。個人間で交渉することになります。
競売物件と公売物件を比べた時、どちらを選ぶかは判断が難しいところです。
物件の状況にもよりますし、リスクの許容度によっても異なります。
物件数でいえば競売物件のほうが多いため、求める物件が見つかりやすいかもしれません。
価格も競売物件の方が割安です。
一方の公売物件は物件数が少ないものの、建物の状態がきれいな物件が多いといわれます。
そのため、購入後のリフォーム・リノベーション費用を抑えられる可能性が高いです。
どちらが良いというより、それぞれの物件情報を見ながら住まいに求める条件に適しているほうを選ぶのが賢明です。
競売・公売物件は、通常の不動産物件の売買とは購入方法が異なります。
ここでは物件情報の探し方と、購入の流れについて解説します。
競売物件も公売物件も、物件情報はインターネットで探せます。
競売物件は「BIT(不動産競売情報サイト)」というホームページに、全国の情報が掲載されています。
ただ、すべての競売物件がBITに掲載されているわけではなく、最寄りの裁判所に足を運んだほうが多くの情報を確認できる場合があります。
公売物件は、国税庁の「公売情報」というホームページをはじめ、各税務署・自治体のサイトに掲載されています。
差し押さえた官庁ごとに物件情報が異なるため、それぞれのホームページで確認しましょう。
このほか、官報や新聞に公告として物件情報が掲載されることもあります。
競売・公売物件の購入までの流れは、以下の通りです。
・BITや公売情報などで物件を探す
・保証金を払って入札する
・開札を待つ
・落札できたら代金を納付する
・所有権移転の手続き後、物件の引き渡し
いずれの物件も、入札期間が決まっています。
期間は短いため、BITや公売情報などのホームページをこまめにチェックすることがポイントです。
入札価格には、裁判所・官庁などが定めた最低基準額が決まっています。
落札するには、その額以上の資金を用意する必要があります。
また、入札時には保証金の支払いが必要です。金額は、最低基準額の2割です。
落札者は、残りの代金を落札時に支払います。
決められた期日までに支払えない時は、購入する権利を失うので注意しましょう。
その後、所有権移転などの手続きは裁判所や税務署などで行います。
競売物件を購入するには、「入札時に必要な保証金」と「それを除いた落札価格」を手元に用意しなければなりません。
この資金を住宅ローンで賄うことも可能ですが、競売物件の購入に利用できる住宅ローンは非常に少ないです。
使える金融機関があっても、競売物件は担保としての価値が低いため、審査が厳しい傾向があります。
そのため、競売物件の購入を検討する時は、全額キャッシュで支払うか頭金を多目に用意する必要があります。
ちなみに、入札時の保証金は自己資金で用意するのが通例です。
通常の不動産売買とは異なり、競売物件には落札してみないとわからない予期せぬトラブルも多々あります。
ここで、よくあるトラブルと対処法について紹介します。
債務者には引き渡しの義務がないため、落札後もそのまま居座り続ける居住者もいます。
そもそも引っ越すお金がなく、仕方なく居座り続けるケースもあるでしょう。
ただ、落札者には立ち退きを要求する権利があります。
居住者と話し合いができるようであれば、引渡しの条件などを協議しましょう。
場合によっては転居費用を渡して、立ち退いてもらうのも一手です。
それでも立ち退かない場合は裁判所に申し立て、引渡命令を出してもらいます。
これにより、強制的に明け渡しの手続きができます。
なお、これにかかる費用は、落札者の自己負担となります。
市場価格より安く落札できる競売物件。
しかし、リフォームやリノベーションの費用が通常より高くなるリスクがあります。
落札後にシロアリ被害などが見つかっても瑕疵担保責任を追及できないため、修繕費用は自己負担になるからです。
こうしたトラブルを避けるには、入札段階で古い家を避けたり、リフォーム費用を多目に用意したりといった対策があります。
内覧もできないため一般の人に瑕疵を見つけるのが難しいこともありますから、不動産会社などのプロに相談して物件を選ぶのも一手です。
居住者のいない物件の中には、部屋に家財道具が残っているケースもあります。
居住者と連絡が取れて引き取ってもらえるのであれば問題ありませんが、夜逃げなどで行方不明となり連絡が取れないというケースもあるのです。
この場合、落札者が勝手に処分することはできません。
処分するには持ち主の了承が必要です。やっかいなのが、居住者が亡くなっていた場合。
残された家財の相続人や管財人を見つけ、処分の了承を得る必要があります。
とはいえ、裁判所に申し立て強制執行の手続き後に落札者が処分することも可能です。
その際に必要な費用は落札者の負担となります。
なお、家財道具の有無についてBITなどの物件情報で確認できることもあります。
家財道具が確認されている物件は避けた方が無難でしょう。
Q.競売物件は本当に安いの?
A.落札価格は、市場の不動産価格の3~4割ほど安くなるのが一般的です。
ただし、リフォームなどの修繕費用、居住者がいる場合は立ち退きにかかる費用、不用品の処分費用など想定外の費用が発生することもあります。
これらを含めると、物件によっては市場の不動産価格と同等になる可能性もあります。
Q.競売物件の入札期間は?
A.通常の入札期間は1週間ほどです。落札者がいない場合は、引き続き入札されますが、長く売れ残ると落札手続きは取り消され、所有権は債務者に戻ります。
Q.引渡しまでの期間は、どれくらい?
A.居住者のいない物件なら、落札後の諸手続きが済めば、すぐに引渡しとなります。
ただ、競売物件には居住者がいるケースがほとんどで、立ち退き交渉に時間を取られることも少なくありません。
場合によっては、落札から数ヵ月から1年以上になるケースもあるため、スケジュールに余裕を持つこともポイントです。
Q.競売物件の「特別売却」とは何ですか?
A.特別売却とは、入札期間中に買い手が現れなかった場合に、先着順で落札者を決める方式です。
落札価格は、裁判所が定める最低基準額ですから、ほかの競売物件よりも安く手に入る可能性があります。
Q.専門家のサポートがあった方が良い?
A.競売物件の落札経験がない方は、専門家に相談されることをおすすめします。
不動産会社や司法書士、弁護士などに、物件選びや入札価格の決め方などを相談しながら進めることで、落札後のトラブルを最低限に抑えられます。
競売物件は、一般的な不動産よりも安く買えるチャンスがあります。
その一方で、内覧ができなかったり設備などの修繕費用は自己負担だったり、居住者が退去してくれずトラブルになったりするリスクも潜んでいます。
こうしたトラブルは落札してみないとわからないことも、競売物件の注意点です。
裁判所やホームページの情報だけでは不明点も多く、安易に手を出さない方が無難です。
不動産会社などの専門家からアドバイスをもらいながら進めることで、リスクを最小限に抑えることも可能ですから、競売物件の取引が初めての方は専門家の力を借りながら検討されてはいかがでしょうか。
永大ハウス工業では、仙台・宮城エリアに特化した戸建て、マンション、土地など様々な不動産を取り扱っております。こだわりの物件はコチラから。

このコラムでは住宅ローン減税の控除額や条件を細かくお伝えしていきます。
2025.06.16

今回は、失敗しない物件選びのための「内見時に必ずチェックしたい10のポイント」を解説します。
2025.06.15

今回は、「頭金ゼロで家を買う」ことのメリットとリスク、その対策までを徹底解説いたします。
2025.06.12

ここでは、「価格動向」「住宅ローン金利の最新情報」「ライフプランから考えるタイミング」を中心に解説していきます。
2025.06.10