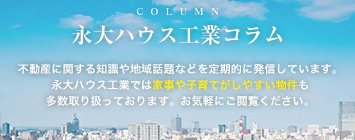戸建てやマンションを購入する際に、親から資金援助を受けるときの注意点は、無計画な資金援助による税金や相続トラブル、家族との不仲を避けることです。
しかし、どのような援助だと税金がかかるのか、どういったケースで住宅資金の補助が相続トラブルになり得るのかを知っていないと、適切な援助を受けられません。
本記事では、親から住宅購入資金を補助してもらう場合に押さえておきたい支援の方法や、それぞれのメリット・デメリット、援助してもらう際に役立つ節税制度などをご紹介します。
家を買う時、親から住宅費用の補助を受けても良いの?
家を買うとき、親から住宅資金の補助を受けられるなら、積極的にサポートをお願いしましょう。
なぜなら、新居に使える予算が増えることで、予算の関係上諦めていた土地や物件に手が届くようになったり、借入額を減らして月々の返済が楽になったりするからです。
また、若年層で家を買うと、ローンの完済も早まります。
40歳で30年ローンを組み、70歳での完済を目指すより、30歳で30年ローンを組み、60歳で完済する方が、老後の負担も軽いです。
ただし、援助の金額や方法によっては、贈与税がかかったり、兄弟姉妹と将来相続で揉めたりすることになるため、事前に親と話し合ってから援助の方法を決めましょう。
親から住宅費用の補助を受ける前に確認した方が良いことは?
●親が新居についてどこまで口を出すつもりなのか
お金を出す条件として、新居について口出しをする親は少なくありません。
たとえば、親の近くに引っ越してくることを求めたり、家の仕様について意見を出してきたり、親の知り合いの工務店で家を建てるようアドバイスしてきたりするケースです。
新居にこだわりのある方だと、アドバイスがきっかけで親との仲が悪くなってしまう場合もあるため、援助を受ける場合はどの程度口出しをするつもりがあるのか、事前にすり合わせておきましょう。
●贈与税がかかるかどうか
通常、年間で110万円以上の現金や資産を贈与すると、援助された側が贈与税を納めることになります。
贈与税は、相続と同等以上に負担が重いため、安易に高額な資金援助を受けてしまうのはおすすめできません。
幸い、親や祖父母から子どもへの住宅資金援助については、通常の贈与よりも大きな額を非課税で贈与できる、税の特例が使えます。
節税制度を使いこなし、負担の少ない金額と方法で住宅資金を補助してもらいましょう。
●援助を受けることでほかの相続人から文句が出ないか
相続トラブルは、お金持ちの家庭だけで起きる話だと考えている方は多いです。
しかし、実際には、「長男だけ大学の学費を出してもらえた」「次男だけ住宅資金を援助してもらった」など、不公平感や不満が引き金となり、相続トラブルに発展するケースが少なくありません。
場合によっては、住宅資金の援助が相続の前倒しと見られ、将来相続できる財産が減ったり、相続税がかかったりすることもあります。
家族の不仲を避けるため、資金援助や相続について、事前に家族で話し合いましょう。
親から住宅費用を補助してもらう方法とそのメリット・デメリット
●現金を贈与してもらう
親から住宅費用を補助してもらう方法として、最もシンプルなのが現金の贈与です。
まとまった額の現金があれば、頭金を多く出して住宅ローンの借入額を抑えられるため、返済負担を抑えられますし、住宅ローン審査にも通りやすくなります。
一方、現金を贈与してもらう方法のデメリットは、原則として年間110万円以上の現金を受け取ると、贈与税がかかることです。
親子間であれば、110万円より大きな額を非課税で贈与してもらえますが、税の特例を受けるためには、贈与税の確定申告をする必要があります。
●不動産を共有する
不動産の共有は、たとえば4,000万円の新居を買う際に、親が1,000万円、子が3,000万円出して持ち分を共有するといった方法のことです。
不動産を共有するメリットは、親が負担額に応じた持ち分を所有していれば、贈与税がかからないこと。
贈与税がかかるのは、何の対価もなく、お金や財産を渡す場合です。
親が1,000万円出す代わりに、家の25%を自分の所有物として登記すれば、親側は不動産という対価を得ているので、贈与にあたりません。
ただし、親が住宅資金の25%を払っているにも関わらず、子の持ち分を100%として登記すると、住宅価格25%分の贈与になってしまいます。
また、住宅ローンは、「自分が住む家を買うためにお金を借りる契約」です。
1,000万円をローンなしで払っていれば同居不要ですが、親子ローンなどの住宅ローンを利用している場合、親も新居に住む必要があります。
名義を共有することで、建て替えや売却にも親の同意が必要になり、介護ついても考える必要があるため、不動産の共有は慎重に決めましょう。
●親からお金を借りて家を買う
住宅購入資金を親に借りるという手もあります。
親からお金を借りるメリットは、親族間なので比較的優しい条件で借り入れを受けられることです。
とはいえ、「返済不要」「返済期限が設定されていない」「無利子」「契約書なし」など、現実的に返済することを考えていない内容だと、贈与とみなされてしまいます。
親子間で借金をする際は、借り入れ書を作り、返済期限・返済額・利子を設定しましょう。
住宅費用を補助してもらうなら知っておきたい!贈与税の基礎知識
●贈与税の基礎知識
贈与税は、第三者から無償でお金や不動産などの財産をもらった時に発生する税金です。
収入に関係なく、110万円の基礎控除があるため、贈与額が年間110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
もともと、財産を生前に贈与することで遺産を減らし、相続税を逃れようとする行為を防ぐために作られた税なので、最高税率は55%と相続税と同じ高さに設定されています。
「住宅取得等資金贈与の非課税特例」「相続時精算課税制度」など、贈与に関する節税制度を利用すれば、よりお得な贈与が可能です。
●贈与税がかかるケース・かからないケース
贈与税がかかるかどうかの基準は、年間110万円以上の贈与があるかどうかの一点で決まります。
ただし、贈与の対象は、現金だけではありません。
親から住宅資金を援助してもらう場合、以下のようなケースだと贈与税がかかります。
- 住宅購入資金として、親から現金200万円援助してもらった
- 生活が安定するまで、住宅ローンを親に肩代わりしてもらった
- 親が持っている土地や、親が購入した住宅をタダで譲ってもらった
一方で、援助を受けたとき、贈与税がかからないのは以下のようなケースです。
- 3年間毎年110万円ずつ援助してもらい、330万円を家の頭金にした
- 結婚や出産などの祝いごとがあった時、社会通念上妥当な金額をもらった
- 親と不動産を共有する
- 借用書を書き、親から借金する
なお、子どものお小遣いや生活費、教育費などは贈与になりませんが、生活費・教育費などの名目で親から受け取ったお金を住宅購入に使うと、贈与税の対象になります。
贈与税の税率と計算方法
贈与税の税率は、一般税率と特例税率の2種類です。
親・祖父母から子・孫への贈与は、特例税率が適用されます。
| 基礎控除後の贈与額 |
税率 |
控除 |
| 200万円以下 |
10% |
- |
| 400万円以下 |
15% |
10万円 |
| 600万円以下 |
20% |
30万円 |
| 1,000万円以下 |
30% |
90万円 |
| 1,500万円以下 |
40% |
190万円 |
| 3,000万円以下 |
45% |
265万円 |
| 4,500万円以下 |
50% |
415万円 |
| 4,500万円~ |
55% |
640万円 |
贈与税の計算方法は、以下の通りです。
・(贈与額-110万円)×贈与税率-控除
仮に、家を買うために親から500万円現金でもらった場合、
・(500万円-110万円)×15%-10万円=48.5万円
を納税する必要があります。
親から住宅費用の補助を受けるときに使える制度
●直系尊属からの住宅取得等資金贈与の非課税特例
「住宅取得等資金贈与の非課税特例」は、自分の親や祖父母から住宅資金を援助してもらう場合、新居の省エネ性能・耐震性能・バリアフリー性能のどれかが基準を超えていれば1,000万円まで、省エネ等基準をクリアしていなければ500万円まで非課税で贈与できるという制度です。
ただし、利用するためには、以下のような厳しい要件をクリアする必要があります。
- 2026年12月31日までに贈与が行われていること
- 贈与を受ける側が18歳以上であること
- 親または祖父母から子・孫への贈与であること
- 援助を受けた年の所得が2,000万円以下
- 過去数年間同じ特例を利用していないこと
- 配偶者や親族などの親しい相手ではなく、第三者から家を買うこと
- 援助してもらったお金は翌年の3月15日までに全額住宅購入に使うこと
- 贈与を受けた翌年3月15日までに新居へ引っ越すこと
贈与を受ける側・する側の条件だけでなく、贈与されたお金で購入する住宅にも要件があるため、注意が必要です。
- 住宅の床面積が40平方メートル~240平方メートル以下であること
- 援助を受けて買う家の半分以上を本人の住居にすること
- 新耐震基準をクリアしていること(中古物件の場合耐震改修でも可)
住宅取得等資金贈与の非課税特例は、あくまでも親の援助を受けて子どもがマイホームを持つための特例なので、親の援助で投資用物件や事務所、店舗などを持ったり、住宅購入以外の用途でお金を使ったりできないようにルールが作られています。
なお、この特例は、いつまでも使えるという保証がありません。
もともと2003年に制定されたもので、常設ではなく数年ごとに期限が延長されているため、使えなくなる可能性もあります。
節税の特例は、改正ごとに要件や非課税枠が変わるケースが多いです。
その都度、最新の利用要件を確認しましょう。
●相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、贈与された額を遺産総額へ上乗せし、将来の相続税負担を増やす代わりに、最大2,500万円まで非課税で贈与を受けられるという制度です。
贈与額が2,500万円を超えた部分に関しては、一律20%の贈与税がかかります。
贈与税の最高税率は55%なので、短期間で大きな金額を援助してもらう時、得する制度です。
なお、贈与の制度には、相続時精算課税制度と暦年贈与があり、一度、相続時精算課税を選択すると、暦年贈与には戻れません。
ただし、贈与の制度は贈与をする側が一人ひとりどちらを使うかを選べるため、たとえば、父親から相続時精算課税で贈与してもらい、母親から暦年贈与で贈与してもらうといった使い分けは可能です。
また、もともと相続時精算課税には110万円の基礎控除がなかったのですが、2024年の税制改正によって、相続時精算課税制度を選んでも110万円の基礎控除を受けられるようになりました。
相続時精算課税制度を利用する場合、以下の条件をクリアする必要があります。
・60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与であること
・贈与の翌年に、税務署へ相続時精算課税の届出書を提出すること
住宅費用の援助と暦年課税制度は併用できる?
暦年課税制度とは、贈与税の課税方式のことです。
贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2種類があり、両者は併用できません。
ただし、住宅資金を最大1,000万円まで非課税で贈与してもらえる「住宅取得等資金贈与の非課税特例」は、暦年課税・相続時精算課税のどちらとも併用可能です。
暦年贈与と併用する場合、「110万円+500万円または1,000万円」まで贈与が非課税になり、相続時精算課税と併用する場合、「2,500万円+110万円+500万円または1,000万円」まで非課税で贈与してもらえます。
親に住宅購入資金を援助してもらうときの注意点
親に住宅購入資金を援助してもらうときの注意点は、適切に申告・納税を行うことです。
基本的に、年間110万円以上の贈与を受けると、贈与を受けた翌年に確定申告をする必要があります。
また、贈与税の申告は、住宅取得等資金贈与の非課税特例の利用条件にもなっていますし、相続時精算課税を利用する場合、初年度に届出書の提出が必要です。
申告を忘れると、贈与税を節税する特例を利用できなくなったり、脱税の疑いで税務署に調査され、延滞税や加算税を課されたりするため、気を付けましょう。
まとめ
親から住宅資金を援助してもらう際の注意点は、できるだけ贈与税の負担を抑えつつ、贈与による相続トラブルを避け、申告漏れを防ぐことです。
住宅資金の贈与は、親の老後資金にも影響を与える大きな援助ですし、無計画に贈与を受けると、想定以上の税金がかかってしまいます。
贈与を受けたことで兄弟姉妹と相続時に揉めないよう、また計画的に節税できるように、贈与や相続について家族と話し合い、住宅取得等資金贈与の非課税特例などを駆使して、お得に援助してもらいましょう。