
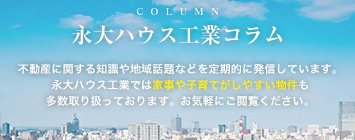
|
<< 2026年1月 >>
月間アーカイブ
|
column 743.
建築面積とは?敷地面積や延床面積との違いもわかりやすく解説2021-04-07
建築面積とは?敷地面積や延床面積との違いもわかりやすく解説
不動産広告などで見かける「建築面積」「延床面積」「敷地面積」といった不動産用語。 ここでは各用語の定義から、建ぺい率や容積率との関係、さらにバルコニーや車庫の取り扱いまで、法的な視点を踏まえてわかりやすく解説します。 建築面積・延床面積・敷地面積とは?まずは、建築面積、延床面積、敷地面積などの広さを表す用語の定義を解説します。 建築面積(建坪)
建築面積とは、「建物を真上から見た時の面積(水平投影面積)」を指す言葉です。
建築面積は一般的に、1階の面積が該当します。 延床面積(建物面積)
延床面積とは、建物の各階の床面積を合計した広さです。
建築面積に似た言葉ですが、延床面積のことですから混同しないように注意しましょう。 敷地面積(土地面積)
敷地面積とは、「土地を真上から見た時の面積(水平投影面積)」を指す言葉です。
敷地面積は、建ぺい率や容積率を求める時の元となる指標です。 建築面積と建ぺい率の関係性
その土地に建てられる建物の建築面積を求める上で、「建ぺい率」は重要な指標になります。 建ぺい率の計算式 建ぺい率
=
建築面積
÷
敷地面積
×
100(%)
建物が建てられるすべての土地には、用途地域などに応じて建ぺい率の上限が決まっています。
たとえば、建ぺい率が60%の地域で敷地面積が100坪の土地の場合、建築面積は最大で60坪までしか建てられないことになります。 バルコニーや庇、テラス、外廊下などの建築面積の扱い
建築面積は「建物を真上から見た時の面積」ですから、外壁から突き出したベランダやバルコニー、庇、テラス、外廊下といった空間も含まれます。 ベランダ・バルコニー・庇ベランダやバルコニー、庇は、「先端から1メートルの部分までは、建築面積から除外できる」という建ぺい率の緩和措置があります。 具体例:外壁から2メートル突き出たベランダ・バルコニー
なお、建築仕様によっては1メートル以内のベランダなどでも建築面積に含まれることがあります。 テラス
テラスは、建物から独立した構造物とみなされるため、建築面積には算入されません。 外廊下
マンションなどの共用廊下で、屋根がなく柱で支えられているような場合は、原則として建築面積には算入されません。 車庫・カーポートの建築面積
車庫やカーポートも、構造によって建築面積の扱いが変わります。 建ぺい率が緩和される条件このほかにも、自治体などによっては建ぺい率の緩和措置が適用される物件もあります。 緩和されるケース(例)
この角地は、交差点や道路、公園、河川などに一定以上の割合で接している土地など、細かな規定が定められています。 延床面積に含まれない空間・設備は?
建築面積と同じく延床面積にも、敷地面積に応じて上限が設けられています。 容積率の計算式 容積率
=
延床面積
÷
敷地面積
×
100(%)
容積率がオーバーした延床面積の家は、違法建築とみなされます。 ベランダ・バルコニー
奥行き2メートル以内のベランダやバルコニーは、原則として延床面積には含みません。 ロフトロフトは以下の条件を満たす場合、延床面積にカウントされません。 延床面積に含まれない条件
たとえば、床面積が50平方メートルのフロアの場合、ロフトの広さが25平方メートル未満、天井高が1.4メートル以下であれば、延床面積に含まれません。 吹き抜け
吹き抜けは、そもそも上階部分の床面積がありません。 出窓出窓も、以下の条件を満たすことで延床面積に含めることなく設置できます。
見付面積とは、外壁から突き出た部分の壁面積のことです。 ビルトインガレージ
ビルトインガレージは、「延床面積の5分の1までの広さ」であれば、延床面積に含まれません。 地下室以下の条件を満たす地下室も、延床面積に含まれません。
上記以外にも細かい規定がありますから、地下室を設置予定の方は不動産会社などに確認しましょう。 その他(玄関ポーチ・屋外階段など)
このほか、玄関ポーチも延床面積には含みません。 まとめ
建築面積・延床面積・敷地面積などの広さに関する言葉は、これから家を建てる方だけでなく、将来の増築・リフォームにも重要な情報です。 夢のマイホームを実現するには、それぞれの面積の正しい意味を理解した上で、建ぺい率や容積率との関係など基本的な情報を覚えておくことも大切です。 マイホームを検討されている方は、不動産の用語や知識にも興味を持ち、一つひとつ学んでいきましょう。 わからないことがあれば、当社スタッフが丁寧にお伝えいたします。 |