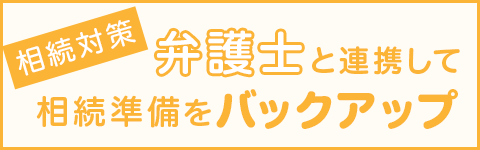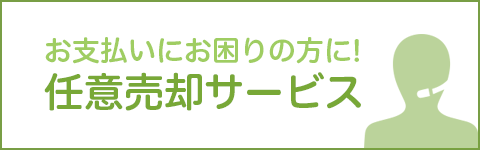不動産売却後の確定申告を自分で行う方法は?手続きの流れを解説
2023.12.15
不動産売却後の確定申告を自分で行う方法は、譲渡所得の内訳書と確定申告書を作成し、郵送・直接提出・e-Taxといった手段で税務署に提出するだけです。
ただし、普段確定申告を会社が代行してくれている会社員からすると、確定申告は馴染のない手続きです。
提出書類に不備があると損をしますし、最低限の知識がないと、そもそも納税や確定申告が自分に必要なのかも判断できません。
そこで、この記事では、不動産売却後に確定申告を自分で行うために知っておきたい、確定申告の基本や手続きの流れについて解説します。
申告の期限は?費用や申告方法は?確定申告の基本を解説
●確定申告とは
確定申告とは、1月1日から12月31日までに手に入れた所得と納税額を自分で計算し、税務署に申告する手続きのことです。
会社勤めをしている場合、会社側が月々の給与や各種控除を計算し、本人に代わって所得税の申告や納税をしてくれるため、会社員だと一度も確定申告をしたことがないという方もいるでしょう。
しかし、不動産売却で手に入れた利益である譲渡所得は、会社が把握していない収入なので、家や土地を売って利益を得た場合、譲渡所得や譲渡所得税を自分で申告する必要があります。
●譲渡所得の計算方法
譲渡所得の計算方法は、「売却価格-(取得費+譲渡費用)」です。
取得費には、不動産の購入代金や登記手続きにかかった費用などが含まれ、譲渡費用には売却時に支払う仲介手数料や登記費用が含まれます。
もし、不動産を3,000万円で売却し、取得費も譲渡費用も良くわからないからといって「0」と記入して確定申告すると、「3,000万円×◯%」の譲渡所得税が発生するわけです。
取得費や譲渡費用が正確に分かれば、課税所得を減らし、税の負担が軽くなるため、不動産を売るときは、取得費や譲渡費用の証明になる書類を準備しておきましょう。
●長期譲渡所得・短期譲渡所得の違い
不動産売却の結果、譲渡所得が黒字になる場合、譲渡所得税の納税を求められます。
譲渡所得税は、いわゆる給与に対する所得税とは、課税ルールが異なる税金です。
不動産を売却した年の1月1日時点で、不動産の所有期間が5年を超えている場合は、「長期譲渡所得」(所得税15%+住民税5%)となり、5年以下の場合「短期譲渡所得」(所得税30%+住民税9%)が課税されます。
●確定申告の手続き期限は不動産を売った翌年の3月15日
確定申告の手続き期限は、原則として不動産を売った翌年の3月15日までです。
確定申告は、毎年2月16日~3月15日までの1ヵ月が申告期間となっており、期間内に申告手続きを終わらせる必要があります。
期限内に申告できなかった場合、「無申告加算税」や「延滞税」を課されたり、譲渡所得税を大幅に減税できるお得な節税制度を利用できなくなったりするため、早目に準備を始めましょう。
●確定申告をする際にかかる費用
不動産売却後の確定申告を自分で行う際にかかる費用は、数百円から1,000円前後です。
税務署に提出する書類は、税務署の窓口に無料で置いてありますし、国税庁のホームページからダウンロードして印刷できます。
ただし、節税の特例を利用する際、住民票や登記事項証明書といった公的な書類の提出を求められた場合、数百円程度の手数料が必要です。
また、確定申告書類を郵送する際は、切手代や封筒の購入費用もかかります。
確定申告を税理士に依頼する際の相場は、5~10万円が一つの目安なので、手続きを自分で行うだけでも節約可能です。
●確定申告書類の提出方法
確定申告書類の提出方法には、以下の3通りがあります。
・税務署または税務署が設置する申告会場に書類を持参する
・税務署に郵送する
・e-Taxで申告する
直接提出のメリットは、申告会場に税理士が待機しており、期間内なら無料で税理士に提出書類をチェックしてもらえることです。
大抵の場合、会場が混雑するため手間や時間はかかりますが、安心感を重視するなら直接提出を選ぶと良いでしょう。
郵送は、申告書類を紙で提出したい方、電子申告をしたくない方向けの申告方法です。
一方、e-Taxは、マイナンバーカードとマイナンバーカードを読み取れるICカードリーダー、またはスマートフォンがあれば申告書を作成できるサービスです。
特にこだわりがなければ、e-Taxの利用をおすすめします。
不動産売却後に確定申告が必要かどうかの見極め方
●不動産売却で利益が出たら確定申告が必要
不動産売却をした結果、譲渡所得が黒字の場合、譲渡所得税が発生するため確定申告が必要です。
ただ、不動産の売却価格から、取得費・譲渡費用を差し引くと利益が0以下になる場合、不動産を売っても確定申告をする必要はありません。
不動産売却後の譲渡所得が20万円以下で、なおかつ本業以外に収入を持たない会社員の場合、多少、利益が出ていても確定申告が免除されます。
●税や控除の特例を利用する場合は確定申告が必要
譲渡所得税に関する控除の特例を利用する場合、利益があってもなくても確定申告が必要です。
なぜなら、特例の利用条件に、「確定申告すること」が盛り込まれているから。
「マイホームの売却なら譲渡所得から3,000万円控除できる制度」や「所有期間が10年を超えていると税率が安くなる制度」などを使いこなすためにも、確定申告を実施しましょう。
確定申告を自分で行うときの流れを解説
●必要書類を揃える
不動産売却後の確定申告手続きに必要な書類は、以下の通りです。
・譲渡所得の内訳書
・確定申告書
・売買契約書
・登記事項証明書
・取得費・譲渡費用の証明になる領収書等
・本人確認書類
e-Taxであれば、一部書類の提出を省略したり、PDFで提出したりできます。
なお、書類に不備があると、申告手続きを進められません。
抜け・漏れのないように、必要書類を揃えましょう。
●譲渡所得の内訳書と確定申告書を作成する
譲渡所得の内訳書は、売却した不動産の詳細と、売却代金や取得費・譲渡費用を記入する書類です。
合計5ページ分あり、順番通りに記入していくと譲渡所得を計算できます。
譲渡所得の内訳書を記入したら、確定申告書類の作成です。
1年間の給与所得や国民年金・国民健康保険等の社会保険料などを記入します。
何をどこに記入すれば良いかわからない場合、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を参考にすると良いでしょう。
●確定申告書類を提出する
窓口・郵送・e-Taxなど、お好みの方法で確定申告書類を提出すれば、手続きは終了です。
確定申告をした結果、納税の必要があれば必要額を支払い、還付金がある場合は、指定した金融機関の口座に振り込んでもらえます。
なお、還付金の振り込みは、e-Taxでの手続きが一番早いです。
一度提出した申告書類の修正も簡単にできるので、こだわりがなければ確定申告書等作成コーナーを利用して、e-Taxを行いましょう。
不動産売却後の確定申告で頼りになる税の特例制度
●マイホーム・相続財産を手放すときの3,000万円控除
マイホームの売却や、両親・祖父母から相続した不動産を売却する場合、譲渡所得を最大3,000万円控除できる税の特例があります。
細かな利用条件はいくつかあるものの、「売却するまで自分や家族が住んでいたこと」「過去数年同じ特例を利用していないこと」といった条件をクリアしていれば、大抵の方が利用可能です。
マイホームの売却なら、3,000万円控除だけで納税額がゼロになるケースも少なくないため、積極的に利用しましょう。
●10年超軽減税率の特例
売却した年の1月1日時点で、マイホームを10年超所有していた場合、譲渡所得税の税率が所得税10%+住民税4%に下がる特例です。
所有期間5年超で不動産を売ったときに適用される長期譲渡所得でも、税率は所得税15%+住民税5%なので、軽減税率を利用できると税の負担が大きく下がります。
なお、税率が下がるのは、譲渡所得6,000万円以下の部分です。
譲渡所得が6,000万円を超えた部分については、長期譲渡所得と同等の税率がかかります。
また、軽減税率の特定も、確定申告時の申請が必須です。
売却時の所有期間が10年を超えていれば、自動的に軽減税率が適用されるわけではないため、忘れずに申請しましょう。
●売却したマイホームの買換え特例
マイホームを買い換える場合、本来なら売却時に発生する譲渡所得税の納付を、将来買い換えた物件を手放す時まで保留できる制度です。
納税を将来に繰り延べているだけなので、厳密にいえば節税できているわけではありませんが、買い換え直後の出費がかさむタイミングで、税のことを気にせず家を買い換えられるというメリットがあります。
自分で確定申告する方向けのQ&A
●Q.初めてでもe-Taxで申告できる?
A.問題ありません。
e-Taxは、確定申告が初めての方でも使いやすい行う方でも手続きしやすいように、整備されています。
確定申告書等作成コーナーを利用すれば、質問に答えたり、順番に出てくる項目に数字を入れていったりするだけで、申告書類の作成が可能です。
マイナンバーカードを読み取れるスマートフォンであれば、スマホだけで申告手続きを終えられます。
●Q.手放す物件の取得費が分からない場合はどうすれば良い?
A.取得費がわからない場合、概算取得費といって、「売却価格の5%」を取得費とみなせる制度があります。
ただし、多くの場合、概算取得費より本来の取得費の方が高額です。
節税を考えるなら、取得費の証拠を集めたほうが、負担する税金を抑えられます。
不動産購入時の売買契約書や領収書など、購入時に支払った手数料がわかる書類を揃えましょう。
まとめ
不動産売却後の確定申告は、一見、ハードルが高いと感じるかもしれませんが、実はスマホ1台あれば初めてでもできる手続きです。
ただし、普段目にしない用語が多いため、譲渡所得の求め方や譲渡所得税の仕組みを把握しておくと、戸惑わずに書類の作成を進められます。
知識があれば節税でき、自分で確定申告すれば手数料もほとんどかからないので、早めに準備を始めて、不動産売却後の負担を減らしましょう。