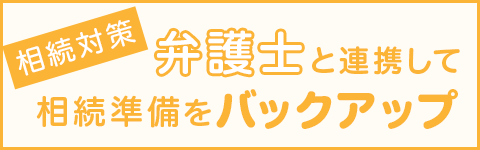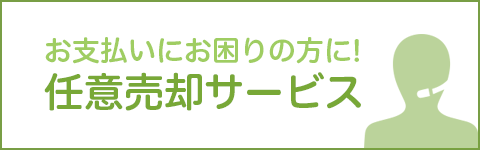譲渡所得って何?総合課税と分離課税の違いも解説
2023.11.06
譲渡所得とは、不動産や車などの資産を売却した時の利益です。
日本では、一定の収入や利益を得ると、利益に応じた税金を納めることが義務付けられています。
しかし、所得には10種類の違いがあり、それぞれ課税の方式や税率が異なるため、不動産を売った後適切な納税をするためには、税に関する理解が必須です。
そこで今回は、そもそも譲渡所得とは何なのかという基本的な話から、総合課税・分離課税と呼ばれる課税方式の違い、譲渡所得と譲渡所得税の求め方などを解説します。
不動産を売るなら知っておきたい!譲渡所得とは?
●譲渡所得とは
譲渡所得とは、不動産や車などの高価な資産、株式などを売却したときに発生する利益です。
具体的にいうと、何らかの資産を売って得た収入から、購入時の経費である取得費、売却時の経費である譲渡費用、そして控除を差し引いたものが譲渡所得となります。
たとえば、不動産を2,000万円で売却し、その取得費が200万円、譲渡費用が200万円だった場合、譲渡所得は1,600万円です。
「所得×税率」で納税額が決まるため、不動産の売却後に税金がかかるのかを自分で確認するためには、譲渡所得を計算できるようになっておく必要があります。
●譲渡所得になるもの・ならないもの
譲渡所得の対象になるのは、土地・建物といった不動産、株式や金の延べ棒・絵画などの高額な美術品、借地権・著作権・特許権・ゴルフの会員権などです。
基本的に、資産として価値のあるものを売って対価を得ると、譲渡所得税が課税されます。
一方、自家用車や衣類、家具などの日用品や、30万円以下の貴金属に関しては、譲渡所得にならないので、売っても譲渡所得税がかかりません。
売却する財産の中身や金額、取引方法によって、譲渡所得になるかどうかが変わる点が、譲渡所得の少し複雑な部分です。
総合課税と分離課税の違い
●総合課税とは
所得税の課税方式は、総合課税と分離課税の2種類に分かれます。
総合課税は、給与所得や事業所得、一時所得といった複数の所得を合算し、その合計額に税率をかけて納税額を求めるという課税方式です。
税率は5~45%の累進課税で、年間の総所得が高くなればなるほど、税率や納税額も高くなります。
たとえば、年間400万円の給与所得を持つ方が、副業で100万円の雑所得を得た場合、500万円に対する所得税がかかるわけです。
●分離課税とは
分離課税は、譲渡所得・利子所得・配当所得といった一部の所得に対してのみ適用される、課税方式を指します。
総合課税では、各所得の合計額で所得税を計算しますが、譲渡所得なら譲渡所得に対する譲渡所得税、利子所得なら利子所得に対する所得税といったかたちで、所得ごとに税額を計算するのが特徴です。
分離課税の所得がどれだけ増えても、給与所得や事業所得といった本業の収入に対する所得税は増えません。
●不動産売却時の譲渡所得は原則分離課税
不動産売却時の譲渡所得は、原則として分離課税です。
ただし、譲渡所得なら絶対に分離課税になるというわけではありません。
実は、不動産と株式以外の財産を売った場合、総合課税が適用されます。
分類としては同じ譲渡所得でも、分離課税と総合課税、どちらが適用されるかによって、利用する税率や最終的な納税額が変わるため、譲渡所得が総合課税になるケースを知っておきましょう。
譲渡所得が総合課税になるケース
●不動産以外の資産を売却した場合
譲渡所得が総合課税になるのは、以下のような財産を売却したときです。
・自家用車以外の車
・船舶
・30万円以上の価値がある絵画・骨董品・貴金属・金地金
・特許権・著作権・漁業権・採掘権・ゴルフの会員権
趣味で持っているもの、コレクションしている財産や個人的な権利を売ると、総合課税が適用されます。
なお、上記資産の売買を事業として行っている場合、手にした利益は譲渡所得ではなく、事業所得か雑所得になる点にも注意が必要です。
事業所得・雑所得は、ほとんどが総合課税なので、事業として資産の売買をしているかどうかによっても、税率や納税額が変わります。
●事業として資産の売却をしている場合
不動産売却後の譲渡所得は、原則分離課税です。
しかし、不動産の売却を事業として行っていると税務署にみなされた場合、「不動産売買ビジネスで事業所得や雑所得を得ている」という扱いになり、総合課税が適用されます。
ここで注意して欲しいのが、不動産の継続的な売買には、宅地建物取引業の免許が必要であること。
免許を持たない者が不動産の売買を繰り返すと、宅建業法違反となり、3年以下の懲役や300万円以下の罰金刑を科される可能性があります。
もし、複数の不動産や投資用の物件を売買する予定があるなら、宅建業の免許を取ることも検討しましょう。
譲渡所得・譲渡所得税の求め方
●譲渡所得の求め方
譲渡所得は、以下の計算式で求められます。
・譲渡所得=不動産売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除
取得費は、不動産の購入時に支払った、土地・建物の代金や仲介手数料です。
同様に、売却時に必要な仲介手数料や測量費は、譲渡費用として利用できます。
もし、取得費を証明できる書類や領収書がない場合、「不動産売却価格の5%」を取得費とするため、覚えておきましょう。
また、譲渡所得を計算するときは、特別控除の有無も重要です。
たとえば、マイホームの売却なら、譲渡所得から3,000万円差し引ける特別控除を利用できます。
金額の大きな控除を使い、譲渡所得がゼロ以下になれば、譲渡所得税はかかりません。
●譲渡所得税の求め方
譲渡所得税は、「売った不動産の所有期間」で税率が変わるという特徴を持っています。
分離課税の場合、不動産を売った年の1月1日時点で、不動産の所有期間が5年以下なら短期譲渡所得、5年超の場合は長期譲渡所得です。
手放す不動産が、どちらの区分に当てはまるかによって、譲渡所得税や住民税の税率が以下のように変わります。
| 譲渡所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 30% | 9% |
| 長期譲渡所得 | 15% | 5% |
復興特別所得税2.1%を加えると、短期譲渡所得の場合は39.63%、長期譲渡所得の場合20.315%の納税が必要です。
譲渡所得に上記の税率をかければ、ご自身の納税額がわかります。
譲渡所得税を抑えるポイント
●長期譲渡所得で売る
譲渡所得税を抑えるためのポイントは、所有期間が5年を超えるまで不動産の売却を待ち、長期譲渡所得で売ることです。
不動産を売った時にかかる譲渡所得税は、短期譲渡所得と長期譲渡所得で、税率に倍近い差があります。
特に、高額価格の高い不動産や、1年待てば長期譲渡所得になる不動産は、売却を急ぐと税の負担が重くなりやすいため、計画的に売却を遅らせましょう。
●取得費と譲渡費用の資料や領収書を取っておく
譲渡所得税の節税対策としては、取得費や譲渡費用を漏れなく計上し、譲渡所得を減らすことが効果的です。
とはいえ、譲渡費用に関しては、売却手続きを進める中で領収書や契約書が集まるため、見落とす心配はありません。
重要なのは、取得費の扱いです。
取得費には、「取得費がわからない場合、売却価格の5%を取得費とみなす」というルールがあります。
大抵の場合、不動産売却価格の5%は本来の取得費よりも少額です。
取得費を適切に計上できれば、譲渡費用を減らして節税できるため、不動産を売る時は、購入時の売買契約書や領収書を探しておきましょう。
●税の特例を使う
単純な節税効果という意味では、譲渡所得税の特例を使用するのが一番です。
利用条件はありますが、最も節税効果の大きな税の控除を使うと、譲渡所得を3,000万円減らせます。
大抵の不動産は、譲渡所得を3,000万円減らせば譲渡所得がゼロになりますし、高額な物件であっても、譲渡所得が3,000万円減る影響は大きいです。
なお、譲渡所得税の特例は、確定申告の際に申請する必要があります。
譲渡所得の計算時に使える節税制度
●3,000万円の特別控除
3,000万円の特別控除は、マイホームを売る時に使える節税の控除です。
利用する場合、以下のような条件を満たしている必要があります。
・マイホームの売却であること
・以前住んでいた家を売る場合、引っ越してから3年以内の売却であること
・家を売る年とその前の2年間、譲渡所得税の節税特例を使っていないこと
・不動産を家族など特別親しい相手に売っていないこと
空き地や別荘などの売却だと使えませんが、直前まで住んでいたマイホームの売却なら、多くの方が使える制度です。
また、故人が住んでいた空き家を相続し、売却する場合も、3,000万円の特別控除を利用できます。
●マイホームを売ったときの軽減税率
マイホームを売った時の軽減税率の特例とは、長期譲渡所得よりもさらに低い税率が適用される特例のことです。
具体的に説明すると、売った年の1月1日時点で、マイホームの所有期間が10年を超えている場合、譲渡所得税の税率が以下のように下がります。
| 譲渡所得 | 譲渡所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 6,000万円以下の部分 | 10% | 4% |
| 6,000万円超の部分 | 15% | 5% |
通常の長期譲渡所得税率が、復興特別所得税を含めて20.315%なので、5%以上の節税が可能です。
●マイホームの買い換え特例
マイホームの買い換え特例を利用すると、不動産を売ったときに発生する譲渡所得税の納付を、将来買い換えた住まいを手放す時まで保留できます。
税金が安くなるわけではないのですが、家の買い換え時は何かと出費が増えるため、支払いタイミングをずらせるのは大きなメリットです。
特例を利用するためには、10年以上住み、なおかつ10年超所有している不動産を売却し、売却後3年以内に買い換える必要があります。
まとめ
譲渡所得は、不動産を始めとした各種資産を売却した時の利益です。
不動産と株式の売却は、給与所得や事業所得とは別枠で税額を計算する分離課税が適用されるため、不動産を売るときは譲渡所得がいくらなのか、譲渡所得税が発生するかを計算しましょう。
税の仕組みを理解しておけば、売却のタイミングを見極めたり、取得費や譲渡費用を積み上げたり、税の特例を使ったりして節税できます。
税の負担を最小限に抑えて、不動産売却を成功させましょう。