
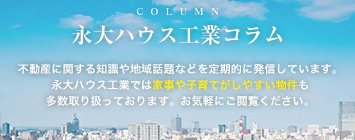
|
<< 2026年2月 >>
月間アーカイブ
|
column 874.
マンション・アパートの水漏れはどうする?原因や対策・対処法を解説2023-11-07
マンションやアパートといった集合住宅で水漏れが発生すると、自宅だけでなく階下の住人にも被害を及ぼす可能性があります。 今回は、マンションで発生しやすい水漏れの原因と対処法を解説するとともに、責任の所在や修理費用、予防方法などもお伝えします。 マンションで水漏れが発生したらどう対処する?マンションで水漏れが発生したら、被害を最小限に抑えるために応急処置をした上で、必要なところへ連絡することが大事です。 詳しく説明しましょう。 ●応急処置をする
水漏れの発生源が自宅の場合、まず水道の元栓(止水栓)を閉じます。 天井から水滴が落ちてくるなど発生源がわからない場合は、漏れている箇所をタオルで押さえたりバケツで水を受けたりして、応急処置をします。
家財が近くにある場合は、水漏れ箇所から離したりビニールシートなどで養成したりして、守りましょう。 また、被害が出ている時は、その状況を写真に撮っておきます。 ●管理会社・管理組合に連絡する応急処置を行ったら、管理会社や管理組合に連絡します。
原因が自分にある場合、階下などの住人にも迷惑をかけているかもしれません。 ●保険会社に連絡する被害が出た時は、保険が使える可能性があります。
一例として火災保険の場合、水漏れ補償が適用されることがあります。 加入している保険の補償内容を確認した上で、保険会社に連絡しましょう。 【場所別で見る】マンションにおける水漏れの原因マンションで水漏れが発生しやすい箇所と、主な原因を見ていきます。 ●トイレの水漏れ住み替えローンは、「旧居のローン残債」と「新居の購入費用」を借り入れるため、必然的に借入額が多くなります。
トイレの水漏れで最も多い原因が、「排水管の詰まり」。 ほかにも、便器やタンクのシーリング破損、配管の接続部分のトラブルなどで、水漏れが発生するケースもあります。 ●キッチンの水漏れキッチンの水漏れは、シンクや蛇口、排水管などの故障によって起きることが多いです。 キッチンのシンクには、日常的に食材のカスや油などが流れ込むため、長年使っていると少しずつ排水が悪くなり、詰まりやすくなります。 また、蛇口やシンク下の排水管自体が劣化すると、蛇口を閉めても水が漏れたり、水を流した時にシンク下の収納が濡れたりすることがあります。 ●洗面所の水漏れ洗面所は水漏れのトラブルが少ない場所ですが、蛇口や排水管の劣化などで生じることがあります。
洗濯機周りも、注意が必要です。 ●浴室の水漏れ
シャワー・バスタブ・排水口の劣化や詰まり、故障によって水漏れが起こります。 また、水まわりのシーリングが剥がれたり固定部が緩んだりした結果、シャワーや蛇口の接続部から水漏れが止まらないといったトラブルも見られます。
不注意によるミスが、思わぬトラブルになるケースも。 ●天井の水漏れ天井から水滴が落ちてくるのは、上階の水漏れや配管トラブル、雨漏りなどが原因です。
上階の水漏れや雨漏りであれば原因をつかみやすいものの、配管だと目に見えない部分なので予防ができません。
天井からの水漏れは、家電製品やコンセントに水がかかる可能性があります。 ●ベランダ・バルコニーの水漏れ排水溝に枯れ葉などが詰まったり、水を流す掃除をしたりすることがきっかけで起こります。
特に、ベランダやバルコニーで水を使う時は注意が必要です。 ベランダやバルコニーは、大量の水を使う想定で設計されていませんので、水を使うのは避けた方が無難です。 水漏れの責任の所在はどのように決まる?マンションで水漏れが発生したとき、責任の所在は「原因」と「発生箇所」によって異なります。 たとえば、住人の不注意で水漏れが発生したことが明らかな場合は、その住人が責任を負うことになります。
では、配管トラブルなど設備の不具合で発生した水漏れだと、どうでしょうか。 一例として、トイレで大量のトイレットペーパーを流して配管詰まりを起こし水漏れが発生したときは、そのトイレを使っている住人が責任を負うことになるでしょう。 なお、専有部の設備でも管理組合がメンテナンスすると規約で決まっていたり、自然災害で水漏れが発生したりするケースでは、管理組合に責任があります。
また、新築物件で配管から水漏れが発生している場合、施工不良の可能性があります。
いろいろ調べても、水漏れの原因が特定できない場合は、責任の所在は管理組合にあります。 マンションで水漏れが発生した際の修理費用水漏れの修理費用は、程度や被害状況によって大きく異なります。
仮に、居宅には被害がなく配管を修理するだけであれば、配管工事費のみとなります。 しかし、水漏れによって居宅の天井や内装が傷んだり、家財を廃棄しなければならなくなったりすると、100万円以上の賠償が生じることもあります。
マンションの水漏れは、自宅だけでなく隣家にも損害を与えることがあります。 水漏れの被害を防ぐには?
水漏れは、住人がしっかり管理していれば防げる事象もあります。 また、万一に備えて緊急連絡先を調べておいたり、保険に加入したりすると安心でしょう。 ここで、水漏れの予防策をまとめておきます。 ●水まわりの状態を定期的にチェックする
目に見える配管は、定期的にチェックするよう心がけましょう。 ほかにも「配管に水滴がついている」「床に濡れた跡がある」といった気になる点があれば、水道業者などに相談し対処してもらいましょう。 ●小まめに掃除する
配管の詰まりなどを小まめに取り除くことも、水漏れを防ぐ上で有効です。 また、洗面台やキッチンシンク下の収納といった配管まわりを整理整頓していれば、定期的なチェックの際に異常に気づきやすくなり、早目に対応できるでしょう。 ●緊急連絡先を調べておく
万が一、水漏れが起きたときに備えて、緊急連絡先を調べておくことも大切です。
なお、自分で水道業者を呼んで修理するのは、おすすめできません。 ●個人賠償責任保険に加入する
水漏れの被害は、さまざまなケースが想定されます。
こうしたリスクに備えて、個人賠償責任保険への加入も検討したいところです。 まとめ
マンションやアパートの水漏れは、定期的な掃除や部品のチェックで、ある程度は予防できます。
そこで重要なのが、日頃からの備え。
|