
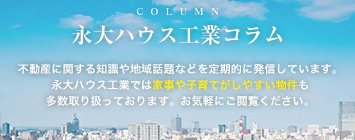
|
<< 2026年1月 >>
月間アーカイブ
|
column 833.
鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)、鉄筋コンクリート造(RC造)と鉄骨造(S造)の違いとは?知っておきたい構造の違い2023-02-14
マンションやアパートといった集合住宅の構造には、「鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)」「鉄筋コンクリート造(RC造)」「鉄骨造(S造)」などがあります。 ここでは、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)、鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨造(S造)の違いについて、これだけは知っておきたいポイントを解説します。 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)・鉄筋コンクリート造(RC造)・鉄骨造(S造)とはまず、それぞれがどのような構造なのかをお伝えします。 ●鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)とは
鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)とは、鉄骨と鉄筋コンクリートを組み合わせた構造です。
この特徴から、タワーマンションなどに採用されることが多いです。 ●鉄筋コンクリート造(RC造)とは鉄筋コンクリート造(RC造)は、鉄筋とコンクリートを組み合わせた構造のことです。
一般的にコンクリートのみで作った建物は、高重量には耐えられるものの、引っ張る力がかかると壊れやすいという弱点があります。 ●鉄骨造(S造)とは
鉄骨造とは、柱や梁などの骨組みに鉄骨を使う構造のことです。 鉄骨鉄筋コンクリート造のメリット・デメリット●鉄骨鉄筋コンクリート造のメリット
鉄骨鉄筋コンクリート造の一番の特徴が、耐震性や耐久性が高いこと。
また、鉄骨鉄筋コンクリート造は、柱や梁を細くしても頑丈な建物をつくれます。 このほか、耐火性や防音性でも鉄骨鉄筋コンクリート造の優位性は高いとされます。 ●鉄骨鉄筋コンクリート造のデメリット
一方のデメリットは、コストが高いことです。
コストの高さから、物件数は他の構造の建物より少なく、好条件の物件を見つけにくいこともデメリットといえるでしょう。 鉄筋コンクリート造のメリット・デメリット●鉄筋コンクリート造のメリット
鉄筋コンクリート造も、耐震性や耐久性、防火性などが高い点がメリットといえます。
設計の自由度が高いことも鉄筋コンクリート造のメリット。
近年は強高度コンクリートの登場で、鉄筋コンクリート造のタワーマンションも増えています。 ●鉄筋コンクリート造のデメリット
中高層の鉄筋コンクリート造の建物は、頑丈な鉄骨がないため、耐震性を高めるには柱や梁の鉄筋を太くしなければなりません。
また、建築コストが高いこともデメリット。 鉄骨造のメリット・デメリット●鉄骨造のメリット
鉄骨造の一番のメリットが、建築コストの安さです。
コストが安ければ、その分、購入時の金額や家賃も下がるので、家計の負担を抑えられます。
鉄骨造にはもう一つ「重量鉄骨造」もあります。 ほかにも、通気性が比較的によいため、結露やカビが生じにくいという点もメリットです。 ●鉄骨造のデメリット
鉄骨造は、火事に弱いです。
また、音漏れがしやすいこともデメリット。 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)・鉄筋コンクリート造(RC造)・鉄骨造(S造)はそれぞれ何が違う?それぞれのメリット・デメリットをお伝えしたところで、施工方法や住まいに与える影響といった観点から、建物の違いをみていきましょう。 ●施工方法から見る違い鉄骨鉄筋コンクリート造と鉄筋コンクリート造の違いは、「頑丈な鉄骨の有無」という点です。
鉄骨鉄筋コンクリート造では、頑丈な鉄骨を用いてその周囲に鉄筋を組み、コンクリートを流し込んで施工します。 なお、鉄骨造はコンクリートを用いず、鉄骨を接合しながら施工していきます。 ●耐久性・耐震性から見る違い
耐久性・耐震性がもっとも高いのは、鉄骨鉄筋コンクリート造です。
鉄骨造は耐久性・耐震性が低いという見方もできますが、能登半島地震のような大きな地震にも耐えられる建物もつくれます。 ●耐火性から見る違い耐火性の観点では、鉄骨鉄筋コンクリート造と鉄筋コンクリート造は、ほぼ同じです。
鉄骨造は、不燃材料であるコンクリートを使わないこと、また鉄骨が熱を伝えやすいことなどから、耐火性は低い傾向にあります。 ●防音性から見る違い
防音性に関しても、鉄骨鉄筋コンクリート造と鉄筋コンクリート造は、ほぼ同じです。
防音性は、壁や床の厚さと気密性がポイントです。 ●通気性から見る違い
通気性は、壁や床が薄い鉄骨造が高いといわれます。 鉄骨鉄筋コンクリート造と鉄筋コンクリート造は、気密性が高いため換気に注意が必要です。 ●コストから見る違い
建築コストがもっとも高いのは、鉄骨鉄筋コンクリート造です。 ただし、ランニングコストも含めると、気密性の高い物件は光熱費を抑えられる傾向があるため、トータルコストは鉄筋コンクリート造が安いという見方もできるでしょう。 まとめ
「鉄骨鉄筋コンクリート造」「鉄筋コンクリート造」「鉄骨造」いずれの構造にも、メリットがあればデメリットもあります。
耐震性や耐久性といった安全性の高さを求める人なら、鉄骨鉄筋コンクリート造が向いているでしょう。一般的な安全性があれば良いという方なら、鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建物でも大丈夫です。
ただ、物件によってはこれらの特性が発揮できていないものも少なからずあります。
|