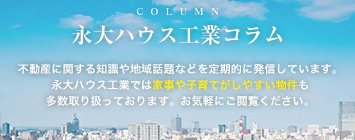日本の伝統的な、「打ち水」が近年見直されています。
「打ち水」とは、江戸時代の庶民の知恵で、道路や庭に水を打つ(撒く)こと。 夏の地面からの熱気を抑えるために地面に水を撒いて、気化熱(水が期待になるときに周りから吸収する熱)を利用して、涼をとるためのものです。
本来は、神様の通り道を清める意味があったそうですが、江戸時代ごろから、夏の涼をとるための実質的な意味が強まったようです。 打ち水の目的には、夏の暑さを和らげることにだけでなく、道の土埃をしずめる、お客様を招くときに玄関先や道に水を撒くことで心地よくお迎えできる、そして日本古来より伝わるお清めの意味、などがあったといわれています。
2000年以降、古き良き日本の風習が、エコの観点からも見直され、各地で打ち水イベントが開催されています。見ているだけでも涼感たっぷりの打ち水ですが、実際に効果も報告されています。 国土交通省が行った打ち水イベントでは、実施前と実施後で、路面の温度が45.3℃から40.6℃に下がったと報告されています。
打ち水を行うときのポイント
国土交通省のサイトには、打ち水について、 雨水や下水再生水などの二次利用水を活用した「打ち水」の生活習慣化は、無理のない節水に繋がり、貴重な水資源の有効利用に結びついています。
さらに打ち水を行うことは、ヒートアイランド対策や、冷房機器の使用減少による温室効果ガス排出量の削減効果も期待できます。
と推奨されています。国土交通省のサイトに「打ち水のルール」が載っていましたので、 一般家庭に関係あるところを抜粋してみました。
打ち水のルール (国土交通省「水の週間一斉打ち水大作戦」より抜粋)
(1)直接に水道水は使わない
水道水の二次利用を基本原則とし、打ち水には、お風呂の残り湯、下水再生水、雨水、エアコンの室外機に貯まった水などを使用する。
(2)お金をかけない
生活の中での水の再利用の促進が目的であるため、ペットボトルや手桶、柄杓、ポリバケツ等の身の回りにある物を用いて打ち水を行う。
(3)涼しげな服装で参加する
江戸時代のエコライフ・伝統文化の見直しという観点から、浴衣を着用したり、クールビズなど涼しげな服装で参加する。
(1)の水道水を使わないというのが肝心で、一般家庭の場合は、お風呂やシャワーの残り水や雨水、台所のすすぎの残り水、米のとぎ汁、子供用プールの残り水などを利用するといいでしょう。
(3)は、イベント参加時のことですが、一般家庭で家の前やベランダなどに打ち水をする際も、浴衣とまではいかなくても、涼しげな服装にすることは心掛けられそうです。
効果的な打ち水には、時間がポイント
気温の高い時間に水をまくとすぐに水が蒸発してしまいます。 打ち水をするなら、比較的気温の低い朝夕がおすすめ。水が熱を逃がす時間が長くなるため、周囲の空気を冷ます時間が長くなり効果的だと言われています。 ちょうどお花の水やりや、子どもや家族を送り出す時間にぴったりですね。
環境にやさしい打ち水で、賢く節電して、暑い夏を心地よく乗り切りたいですね。